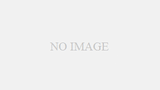こんにちは。S塾長です。
9月も終わりに近づき、中学3年生の皆さんはいよいよ実力テストや模試の荒波に挑む時期となっているかと思います。志望校が決まっている人は、目標校と自分の実力とのギャップをしっかりと確認し、その差をどう埋めていくか?を試験日から逆算して考える時期になっています。
どこまで自分の実力を上げる必要があるのか?それを考えるうえで大切なのは、受験校の試験方式です。今回は大阪府公立高校の選抜制度について書いていきます。
令和7年度入試からの制度変更点
令和7年度入試における大きな制度変更点はありません。
昨年までの方式を踏襲して、次年度の入試も行われます。
ただし、一部の学校では「学力検査の成績:調査書の評定」の割合の変更や、国数英の試験問題(難易度)の変更がありますので、受験校の最新の情報を確認し、準備を進める必要があります。
大阪府公立高校の入試制度
以下の2つの合算により、選抜されます。
- 調査書の評定(いわゆる内申点)
- 学力等検査の成績
>特別選抜に該当する一部の専門科ではこれらに加えて実技試験が実施されます
評定の合計点は受験形式・受験する学科によりさまざまですので、ご自身が受験する可能性のあるところについては確認しておく必要があるでしょう。
いわゆる「普通科」と呼ばれる学科を受験する場合、上記2つの満点はそれぞれ450点、合計900点で選抜されます。ただし、評定と検査成績を1:1で評価するのではなく、学校ごとに定められた比率で計算しなおした結果で合否判断されます…と書いてみると非常にわかりにくい感じになってきます。こちらも受験する可能性のある学校がどのような比率で総合点を算出するのか確認しておく必要があります。
学校によっては「評定:テスト=3:7」としていわゆる試験重視のところもあります。ではテスト重視の学校では本番の試験で逆転が可能でしょうか?
多くの場合、学力的に同等程度の学生が競争相手となります。実力が似たり寄ったりの中で大きく差が付くかというと、そういうことも無いのかなと思っています(もちろん、何事にも例外はあります)。
公立高校の受験を目指す方は、中学1年生から内申点を上げる努力を積み重ねて、有利な評定で受験できるよう毎日頑張っていただきたいものです。
まとめ
令和7年度の大阪府公立高校入試の制度は前年度と同様です。
一部の学校で選択問題の変更や総合点を算出する比率の変更などがありますので、受験可能性のある学校については事前に確認しておきましょう。
3月の入試本番まで残り半年。悔いの残らない準備を進めてくださいね。